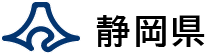実践NOTE556 「子供が主体的に学習に取り組むための園小接続を生かした単元構想と環境設定」
子どもが主体的に学習に取り組むための園小接続を生かした単元構想と環境設定
掛川市立桜木小学校 教諭 御園生 綾音
はじめに

掛川市では、「かけがわ型架け橋カリキュラム」の開発を進めながら、合科的・関連的な指導の工夫や日々の生活の中で生まれる子どもの思いや興味を生かした学びの構成、弾力的な時間割の工夫を大切にしています。今回は、「かけがわ型架け橋カリキュラム」を生かして昨年度実施した、1年生の生活科「あきとなかよし」の単元を紹介します。
子どもたちの思いから単元構想を広げる
まず単元に入る前に、園の職員と1年担任で情報交換をしました。1年生が、年長時に経験した秋の活動、秋探しをした場所、園の日常生活を聞き、単元を構想する際の参考にしました。主体的に学習に取り組むためには、子ども自身が秋の特徴や様子を理解して、秋の自然物で遊ぶ面白さや不思議さを感じられる時間と、自分が楽しんだことを他者に伝える時間が大切であると考え、2つの小単元で構想しました。そして、単元を通して、子どもたちの思いを引き出すような発問を意識し、子どもたちの思いや考えに沿って、単元の修正・改善を行いました。

園の環境を生かした安心して活動を広げられる環境設定

子どもたちが安心して活動を広げ、主体的に学習できる場を作りたいと考え、園の環境と同様に、絵本や道具、材料コーナーを設置しました。また、年長時に経験した秋の活動を思い出しながら学習に取り組めるように、各園から集めた秋の活動の写真を掲示しました。さらに、主体的に学習する子どもの写真や振り返りカード等を掲示し、他者と協働的に学習する姿や課題解決のために工夫する姿の価値付けをしました。その結果、一人一人が自分の課題に向き合い、粘り強く活動を進める姿が見られました。
おわりに
子どもの思いや願いを取り入れた単元構想や、園の環境を生かした学習環境は、子どもが生き生きと活動し、学びを広げていくことに繋がると実感しました。今後も、子どもと一緒に単元を構想し、安心して活動を広げられる環境を作っていきたいと思います。

このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3168
ファクス番号:054-221-3561
kyoui_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp