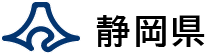認知症について
令和6年5月に発表された厚生労働省の将来推計によると、2040年(令和22年)には、認知症の人は全国で約584万人になると推計されています。これは、65歳以上の高齢者のうち、6.7人に1人の割合となります。
また、軽度認知障害(MCI)を含めると、約1200万人、高齢者の3.3人に一人の割合となります。
このように、認知症は誰もがなり得るものであり、同時に誰もが認知症の人の介護者になる可能性があります。
2024年(令和6年)1月には、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下認知症基本法)が施行され、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することにより、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することが明記されました。
県及び県内各市町においても、認知症基本法の理念に基づき、「認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる社会づくり」のための取組を進めています。
おしらせ、新着情報など
認知症かな?と思ったら
認知症のことや介護・福祉・医療に関することなど、どこに相談していいかわからない場合は、まずは、お近くの「地域包括支援センター」に御相談ください。
認知症の診断や治療は、かかりつけ医を受診し、必要に応じて専門医を紹介してもらうという流れが基本となります。県及び静岡市・浜松市では、かかりつけ医を対象とした認知症診断の知識・技術、患者・家族への対応等の研修を実施するとともに、かかりつけ医への助言その他の支援を行ったり、地域における認知症医療の連携推進役となる認知症サポート医を養成しています。
県内16か所の認知症疾患医療センターでは、認知症の鑑別診断や専門医療相談等を実施しています。認知症疾患医療センターの受診にあたっては、事前予約が必要です。なお、原則かかりつけ医等からの紹介が必要となりますので。必ず事前に電話で確認してください。
県では、認知症の方や介護されている家族等の悩みや疑問にお答えする電話相談(認知症コールセンター)を週3日実施しています。どんなことでもかまいません。気軽に御相談ください。
県では、認知症の人と家族、医療や介護の専門職が情報を共有する認知症連携パス「ふじのくに”ささえあい”手帳」を作成し、病院・診療所、介護事業者、市町等の協力を得て、全県での普及を図っています。
県内各地で、認知症の人と家族の会、介護家族の会、介護者の集い等が実施されています。同じ経験をしている同士が悩みを話しあったり、情報交換をしたりする場です。開催時期、活動内容等は、地域によって異なりますので、別添を御参照ください。
認知症カフェは、認知症の人やその家族、医療や介護の専門職、地域の人など、誰もが気軽に参加できる「集いの場」です。設置者は、市町や地域包括支援センター、医療機関や介護事業所、NPO法人、ボランティアなど様々な団体に取組が広がっています。開催時期、活動内容等は異なりますので、別添を御参照ください。
若年性認知症に関して
若年性認知症(65歳未満で発症する認知症)については、若年性認知症コールセンター(認知症介護研究・研修大府センター(愛知県))でも受け付けています。
県内市町の認知症施策取組状況
- 認知症初期集中支援チームの運営
「認知症初期集中支援チーム」は、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援等の初期の支援を包括的・集中的(おおむね6ヶ月)に行い、自立生活のサポートを行っています。平成30年度からすべての市町に設置されています。 - 認知症地域支援推進員の活動
「認知症地域支援推進員」は、認知症の容態に応じて、すべての期間を通じて必要な医療・介護及び生活支援を行うサービス機関が有機的に連携できるよう支援し、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行っています。平成30年度からすべての市町に設置されています。 - 成年後見実施機関の設置
「成年後見制度」とは、認知症や障害等により判断能力が不十分な方に対して、法的に権限を与えられた後見人等が財産管理や介護サービス・施設入所の契約など法的な手続きの支援をする制度です。地域における利用促進の体制整備は市町の役割とされ、従来からの後見人のなり手不足に備えた市民後見人の育成・活動支援の体制整備として成年後見実施機関の設置を推進しています。 - 地域の見守りネットワーク
「見守りネットワーク」とは、高齢者や障害者など社会的弱者に対する日常的な見守りを、地域住民や店舗、配達業を行う企業などが連携して行うネットワークのことです。 - 認知症サポーターの養成・活用
認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けをする「認知症サポーター」を養成し、認知症高齢者等にやさしい地域づくりに取り組んでいます。
また、認知症サポーターに対して認知症カフェなどのボランティアや見守り活動への協力等、活躍の場を提供しています。 - 本人・家族への支援の取組
本人と家族の会の活動支援、認知症カフェなどで相談会の実施、介護者のつどいなどを行っています。
認知症を学び地域で支えよう
-
各市町の認知症サポーター養成講座担当課一覧 (PDF 69.1KB)

認知症サポーター養成講座の開催・受講を御希望の場合は、各市町の高齢者福祉担当課までご連絡ください。 -
介護マークとは
こちらから画像ファイル等がダウンロードいただけます。 - 認知症関連の取組の紹介
介護事業所向けの認知症関連研修情報等
医療従事者向けの認知症関連研修情報等
-
認知症サポート医養成研修(外部リンク)

郡市医師会を通じてお申込みください(申込みは終了しました)
認知症関連リンク
-
認知症介護情報ネットワーク(DCネット)(外部リンク)

認知症介護研究・研修センターが運営するホームページで介護に関する様々な情報が得られます。 -
認知症の本人交流ページだいじょうぶネット(外部リンク)

認知症の人「本人ネットワーク」支援委員会が運営するホームページです。 -
公益社団法人認知症の人と家族の会(外部リンク)

-
厚生労働省「認知症への取組み」(外部リンク)

-
WAMNET(ワムネット)(外部リンク)

介護保険サービスを提供する事業者などを検索できます。 -
県社会福祉協議会の地域福祉権利擁護センター(外部リンク)

福祉サービスを上手に利用するための情報提供や利用手続きの支援を受けたいとき、日常的なお金の管理のお手伝いや通帳や証書などの大切な書類の保管などの相談をしたいときなどに御覧ください。 -
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(外部リンク)

成年後見制度に関する情報が掲載されています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2442
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp