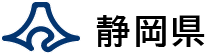認知症の発症を遅らせる環境の整備(遅らせる)
認知症予防には、認知症の発症遅延や発症リスク低減(一次予防)、早期発見・早期対応(二次予防)、重症化予防、機能維持、行動・心理症状(BPSD)の予防・対応(三次予防)があり、「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。
認知症予防に資する可能性のある活動の推進
生活習慣
平成30年度・令和元年度の新規介護認定申請者を調査した結果、介護が必要となった主な原因は、認知症が最も多く、次いで脳血管疾患、悪性新生物の順に多い結果になりました。(令和2年度要介護認定調査における主治医意見書データ集計結果(静岡県健康増進課))
性別でみると、男性は悪性新生物、脳血管疾患の順に多く、女性は認知症、転倒・骨折の順に多い結果となりました。
介護予防のためには、男性は生活習慣病予防、女性はロコモティブシンドローム予防が必要となります。
また、適度な運動や十分な食事と睡眠、知的活動などの生活習慣の改善は、認知症のリスク低減や重症化予防にもつながります。
| 県全体 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 認知症 | 悪性新生物 | 認知症 |
| 第2位 | 脳血管疾患 | 脳血管疾患 | 骨折・転倒 |
| 第3位 | 悪性新生物 | 認知症 | 脳血管疾患 |
難聴
難聴があると、会話がうまくつながらず閉じこもりがちになり、認知症のリスクが高まるという海外の研究もあります。
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会では、難聴を疑ったときに聞こえをたしかめるアプリケーションを紹介しています。
厚生労働省では、自分に合った補聴器を見つけるために、耳鼻咽喉科医(補聴器相談医)に相談の上、補聴器技能者がいる補聴器販売店での購入を勧めています。
新しいつながり
新型コロナウイルス感染拡大の影響で人とのつながりが薄れることによる孤立等を防ぐため、オンラインによる「新しいつながり」を創出するモデル事業を実施しました。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2442
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp