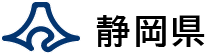県議会だより第129号(3) ピックアップ本会議(1)
行政
令和7年度当初予算編成
Q.県民にとって真に必要な施策をどう反映したのか。
A.県民の命と財産を守る防災・減災対策を強化した上で、中小企業支援や子育て・教育環境の充実等の県民生活に直結する施策に注力する。それらを反映した新年度予算では、道路や河川等のインフラ整備、エネルギーや食材など物価高の影響の大きい農林水産業者や医療機関・福祉施設への支援、県東部地域への医師派遣、男性の育休取得への支援、老朽化した県立学校の建て替え等に取り組む。
次期総合計画の策定
Q.県土の均衡ある発展の実現に向けた策定方針は。
A.「幸福度日本一の静岡県」の実現には、各地域の自然や産業など多様なポテンシャルを最大限に生かして魅力を引き上げることが重要である。令和6年度策定の経営方針では、各地域の資源を活用した地域づくりの基本方向を定める。地震津波対策やこども・子育て施策等、各地域に共通する課題は広域的に対応することも重要であり、令和7年度に策定する行動計画において示していく。
人口減少社会への対応
Q.人口減少に適応した社会構築に向けた取り組みは。
A.人口減少に歯止めをかける対策に加え、豊かな生活を維持・向上させるため、デジタル技術による「社会全体の生産性向上」、子育て中の女性や外国人等の「多様な人材の活躍促進」、市町や企業等と連携した「社会全体の最適化」の3つの視点から積極的な対策に取り組む。県有施設の総量適正化や集約化等に加え、道路等の市町との一括管理など広域連携を進め長期的視点から行政の最適化を図る。
文化・観光
空港を身近に感じる取り組み
Q.富士山静岡空港の需要拡大に向け搭乗しない方にも楽しんでもらう取り組みは。
A.開港15周年を契機に機体見学や遊覧飛行等のイベントを充実したほか、地元食材を扱うテナント開業や伊豆松崎の民芸品展示、開港記念クラフトビールの製造など空港の魅力向上に取り組んだ。令和7年度は人気アニメとタイアップしたイベントで国内外のファンを呼び込む。さらに空港西側にホテルやアウトドア施設等の誘致を目指すなど空港周辺の魅力向上を図る。

ユニバーサルツーリズムの推進
Q.全ての人が安心して楽しめる旅行の推進に向けた取り組みは。
A.高齢者や障害のある方が快適な旅行ができる環境整備に向け、令和7年度に2カ所程度のモデル地域で取り組みを進める。観光関連施設のバリアフリー化に対する助成制度を創設し受け入れ環境の改善に取り組むほか、専門家による相談窓口を設置する。バリアフリー状況等を掲載したデジタルマップの作成や介助依頼等の手配を一括して行うサポートシステムを試行する。
富士山の登山規制
Q.登山規制の実効性を高めるための具体的な取り組みおよび入山料の使途は。
A.富士登山条例で入山者に課す事前学習に富士山の価値や保全、安全登山に必要な心構え等を盛り込む。事前登録した登山者には気象や位置情報を提供するなど安全対策の強化につなげる。入山料は登山規制に係る経費や登山者の安全対策、環境保全に活用する。初年度は規制開始に伴う初期経費が見込まれるが、翌年度以降は受付業務の効率化を進めコスト縮減を図る。
用語解説:富士登山条例
富士登山の規制に関する条例。入山者に、登山に関する事前学習の修了や夜間入山時の山小屋宿泊、入山料の納付などの条件を付す。条例の施行により、登山ルールの理解者の増加や弾丸登山者の減少等の効果を見込んでいる。令和7年2月定例会に条例案が提出され、可決した。
医療・福祉
健康寿命日本一の維持
Q.都道府県別健康寿命日本一の維持に向けた方策は。
A.健康寿命の延伸に向け、高血圧に着目し減塩等の食生活改善や血圧測定の習慣化等により脳卒中の発症を予防する。生活習慣病の発見治療につながる特定健診受診率向上に向け、市町と連携した重点広報や特典付与による受診勧奨に加え、受診率向上に実績がある成果報酬型契約のモデル事業に共同で取り組む。モデル事業で得られたノウハウを他市町等に共有し、県内全体の受診率向上につなげる。
用語解説:健康寿命
健康上の問題により日常生活が制限されることなく生活できる期間。
救急安心電話相談窓口
Q.#7119の運営状況と令和7年度の実施体制は。
A.令和6年10月から平日夜間や土日等に試行的に開設したところ、需要の高さや救急車出動件数の増加傾向の緩和など一定の効果が確認できた。令和7年度は24時間365日に拡充するとともに相談員を増員して本格運用を開始する。地域医療の確保や救急車の適正利用に向け市町との共同事業として実施し、利用者の意見等も踏まえ改善を図る。利用促進に向け各世代に合った効果的な広報を行う。

医師確保対策
Q.県全体における医師不足解消に向けた取り組みは。
A.令和2年度に利用者の県内勤務を義務付ける医学修学研修資金制度の勤務期間を9年間に改正したことにより、令和8年度以降毎年約100人の医師が勤務を開始し、定着者の増加も見込まれる。若手医師受け入れ体制整備に向け専門研修拡充を図るとともに、各病院の診療科ごとの医師不足状況に応じた配置調整を行う。医大進学者の増加や研修資金利用者確保に向け高校生等を対象に説明会を開催する。
このページに関するお問い合わせ
静岡県議会政策調査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2559
ファクス番号:054-221-3572
gikai_chousa@pref.shizuoka.lg.jp