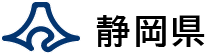第5回伊豆文学賞 佳作「わさびの味」
佳作「わさびの味」
伊藤義行
段々畑となった畳状のわさび田に広がる純白の欠片を目の当たりにすると、宮子は幻を見ているのではないかと錯覚した。目を擦り、大きく息を吸い込み、再び山の緩斜面に視線を這わせると、やはり白い花びらは、瑞々しい姿をさらけ出すわさびの絨毯に中にある。
ひんやりとした渓谷沿いのあぜ道を登り、緑に潤うわさび田を間近に見据える。腰を降ろして両手で水を掬うと、限りなく透明な水玉が指の間からこぼれ落ち、それが水面状で冠のような美しい水飛沫を上げる。彼女は生まれて初めて、わさびの花がサラサラと流れる水流の中に咲くのだということを知った。そして、山頂から流れるその清流と山間の清々しい空気こそが、風味と味で他産のものを圧倒する天城産のわさびに鮮烈な生命を与えているのだということを思い知る。
宮子がわさびの里と呼ばれる中伊豆の天城湯ヶ島町に足を踏み入れたのは、昭和五十四年の春、伊豆半島の真ん中に位置する盆地状の集落に純白のわさびの花が咲き乱れる時期だった。彼女はその美しい景色を体験すると、どんな理由であれ、この土地にやってきたことを素直に喜んだ。
彼女は横浜市の繁華街に店を構える寿司屋に生まれた娘だった。寿司屋というのは気っ風がよくなくっちゃ、そういう父親のざっくばらんな性格を受け継いだ彼女は、幼い頃から長男と次男の間で遊んでいたことも手伝って、端から見ても男と間違えられるほどやんちゃに育った。地元の商業高校を卒業すると、すぐに沼津市にある父の知人が親方をしている「ともえ寿司」に修行に出、そこで厳しくも実りのある青春時代を過ごした。今どき、女の寿司職人は珍しくはないが、当時はコックや板前は男性の職業だと相場が決まっていたので、周囲からの反発には凄まじいものがあった。それでも二十四歳になるまでに、ともえ寿司で一通りの修行を終え、自分で寿司を握ることができるまでになった。あるとき、店の親方と客がわさびの味について議論していた。その論争が宮子のところまで飛び石してくる。
「わさびの味は言葉でいうとどうなるんだろうな」
わさびの味をいい当てる的確な言葉がないのは、今に始まったことではない。一般的な説明では、「甘みがあって、つんと鼻にくる辛味」ということで通っているが、甘みと辛味といっても一般の人間が想像するものとはだいぶ違う。
「宮子の課題だな」
と親方は得意客からの宿題をそのまま彼女に押し当てた。
「ちょうどいい。天城湯ヶ島町へ行って、自然のわさびを見てきな。きっと、いい勉強になるぞ」
宮子もずっと以前から、寿司のネタのよさを引き出す、薬味としてのわさびの使い方には興味を持っていた。いいシャリといいネタを使っても、わさびの付け方を間違えれば、できた寿司は死んでしまうものだが、宮子自身、わさびのすり方の違いで桶の寿司をすべて台無しにしてしまった経験があった。
そういうことで、運転免許を持っていた宮子は、さっそく実家の車を借りて、わさびの産地である天城湯ヶ島町まで出かけた。そこでわさびの本質を掴んで、ちょっとでも一流寿司職人へと近づきたいと思ったわけだ。
「おい、そこで何をしている」
怒号のような男の声に呼びかけられたのが、冷たい清流のせせらぎから手を戻したときだった。ぎょっとして背後を振り返ると、作業服を着た頑丈そうな三十歳前後の男が顔を強ばらせて立っている。どうやら、わさび田を経営している農家の男らしい。宮子が、
「見学です」
と答えると、男は予告もなしに彼女の肩を掴んで、
「出ていってくれ」
と、その身体を押し除けた。
「何故よ。ちょっとぐらい見ても減るもんじゃないでしょ」
宮子は男のあまりにも不躾な態度にかっとなった。
「ところが減るもんなんだ。品種改良の最中だから、やり方を見られると困るんだよ」
「企業秘密というやつね」
静岡県の天城山麓では、良質の水と土壌によって優れた味と風味の沢わさびを生産しているが、目の前の男は、既存の品種に改良を施すことによって、さらに新たなわさびを作ろうとしているのらしい。
「そうだ。だから、さっさと山を降りてくれ」
「わかったわよ」
ふてくされた宮子はやってきたあぜ道を降りると、平野部の道路に停めてあった車まで戻り、そこでともえ寿司の親方が案内を頼んでおいた足立義平太という老人を待ち続けた。足立翁は約束の時間より約五分ほど早くその場所にやって来る。
「沼津のともえ寿司の小林です」
と丁重に挨拶すると、老人は皺を寄せた顔を綻ばせながら簡単にわさび田のことを説明した。日焼けした顔はわさび栽培者の面影を残していたが、すでに引退しているらしく、杖を持って山を歩く仕草はどことなくぎこちないものがあった。
足立翁は先ほど宮子が入った道を上がっていく。途中、彼の息が上がったため、心配顔の彼女がその折り曲がった身体を支えてやった。足立翁は、
「リュウマチだよ」
と苦笑いすると、
「なあに、わさびのほうは息子がやっているから心配はないんだ」
と悲哀のこもった言葉を付け加える。
先ほどと同じ道程で山の急斜面を登っていくと、先刻出会った男が仕事をしている水田に入る。足立翁の息子というのは、宮子の肩を掴んで「出て行け」といった無愛想な三十男のことだったらしい。
「浩介、大切なお得意さんだ。忙しいだろうが、おまえ自身が粗相のないように案内しろ」
リュウマチを患っている父親にそういわれた息子の浩介は、留守番を頼まれた子供のような不満顔で、
「この人が今日来ることになっていたお客さんだったのか」
と父親の顔を一瞥すると、振り向き様に
「一時間だけだぞ」
と宮子に対して目を側めながらいった。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ・文化観光部文化政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2252
ファクス番号:054-221-2827
arts@pref.shizuoka.lg.jp