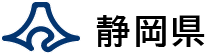駿河湾深層水の有効利用
1.目的
海洋深層水とは、一般的には水深200~300mよりも深いところにある海水のことを指します。太陽の光が届かないため植物プランクトンによる光合成がほとんど行われておらず、浅いところの海水と混ざることがないので、表層水とは違う特性をもっています。日本一深い駿河湾は、最深部が2500mに達します。ここには起源の違う3種類の海洋深層水が存在しています。静岡県では焼津市焼津新港内に取水施設を整備し、黒潮系の海洋深層水を取水しています。海洋深層水は気候変動や人の活動の影響をほとんど受けないため、常に一定の水質を保っています。また、海洋深層水は常に再生産されているため、化石燃料のように枯渇するおそれはないといわれています。
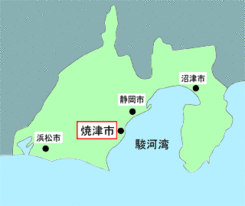
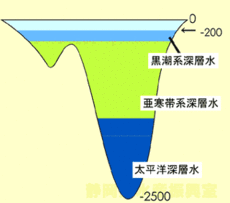
2.海洋深層水の特性
水深200~300m以深の海水は、表層の海水にはない「高栄養性」「清浄性」「低温安定性」という3つの特徴を持っています。
しかし、海洋深層水の持つ、高栄養性、清浄性、低温安定性という資源は、物質的には低品位でエネルギー密度からみた場合もきわめて低いレベルのため、それを有効に利用するための技術を開発する必要があり、県では多分野の研究機関で利用研究を進めています。
高栄養性
硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩が表層水の数倍~数百倍
表層から沈降した生物の死骸等の有機物から、多量の栄養塩類が分解・溶出し、それを利用する植物プランクトンがいないため栄養塩類が豊富ですある。
清浄性
細菌数が表層水の1/10~1/100(病原性微生物が少ない)
餌となるプランクトンが少ないため魚類等の生物が少なく、それらの病気の原因となるような病原性微生物がほとんど存在しません。
また、河川水等から流入する陸由来の環境汚染物質も表層水に比べ極めて少ないです。
低温安定性
水温は年間を通して10℃以下で安定している
表層の水との交流が少ないため、周年にわたり水温が低く安定しています。
海洋深層水は表層の海水が沈降することで生成される、再生循環型の資源です。
3.海洋深層水の利活用
(海洋深層水の利用が期待される分野と具体的利活用例)
- 水産利用
- 有用魚介類の無病種苗生産、養殖(ヒラメ、マダイ、アワビ等)
深海性生物等の種苗生産(タカアシガニ、イセエビ、ウナギ等)
藻類の生産(アラメ、カジメ、クロレラ、スピルリナ等)
漁場環境改善(磯焼け対策、藻場造成等)
水産流通(活魚輸送、蓄養、鮮度保持、魚市場利用等)
水産加工(塩干品等) - 食品利用
- 健康食品(清涼飲料、酒、塩、その他)
食品添加物(カロチノイド類(藻類利用)等) - 医薬医療
- 医薬用薬剤(有用物質等)
海洋療法(タラソテラピー、入浴剤) - 化学
- 有用物質(ミネラル、希少金属類等)
- 農業
- 低温利用(貯蔵、低温性作物、出荷時期調整等)
- エネルギー
- 冷温利用(冷熱源、冷却水、温度差発電等)
- 環境
- モニタリング(海洋環境把握、有害物質把握)
海域環境(海域浄化、CO2固定化等)

このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2744
ファクス番号:054-221-2865
suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp