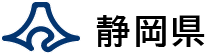令和7年2月定例会意見書(令和7年3月17日可決)
闇バイトによる犯罪の防止に向けた取組のさらなる強化を求める意見書
本文
近年、主にSNSを通じて犯罪の実行役を募る、いわゆる闇バイトによる犯罪が増加し、その形態は特殊詐欺だけではなく強盗や監禁等にまで拡大し、国民の間に不安が広がっている。
闇バイトでは、短期間で高収入が得られるといったSNS上の投稿に安易に応じることで若者が犯罪に巻き込まれる事例が目立っており、中でも秘匿性の高い通信アプリに誘導され、提供した個人情報を理由に犯罪に加担するまで犯罪組織から執拗な脅迫を受ける事案が後を絶たない。
2023年の刑法犯の検挙人員は全国で183,269人で、うち20歳未満の少年は19,399人と全体の10.6%を占めており、前年の9%から増加している。また闇バイトの応募者の7割を10~20歳代が占めていることと合わせると、若者が犯罪に巻き込まれないための対策が急務と言える。
国においては、啓発動画やターゲッティング広告、教育機関への防犯指導等による周知啓発、「警察相談ダイヤル#9110」の運用などによる対策に取り組み、さらに、身分を秘匿して接触する「仮装身分捜査」の運用ガイドラインとなる実施要領が示されたところである。
しかし現状は、闇バイトによる犯罪は後を絶たず、国民の不安解消に至っていない。
よって国においては、闇バイトによる犯罪の防止に向けた取組のさらなる強化に向け、下記の事項に取り組むよう強く要望する。
記
- 闇バイトの実態について、社会的認知度を格段に向上させるため、より訴求力の高い広報啓発を実施するとともに、広報活動の充実・強化を図るための予算を確保すること。
- 現在運用している「警察相談ダイヤル#9110」に加え、若者が使い慣れているSNS等を利用した相談窓口を設置するなど、相談体制の拡充を図ること。
- 仮装身分捜査の実施要領が示されたことから、早期に実施体制を整備し、速やかに実行に移すこと。
- 秘匿性の高い通信アプリが悪用されるという事案もあることから、捜査において必要がある場合には、アプリを運営する事業者に対し、個人情報等の公開を義務づける法整備等の検討を早急に進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月17日
提出先
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 内閣総理大臣
- 総務大臣
- 財務大臣
- 国家公安委員会委員長
- 警察庁長官
リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の処遇改善を求める意見書
本文
リハビリテーションの目的は、事故やけがによる身体機能不全の回復に加え、高齢や脳の病気による心身機能低下を改善させることである。
昨今では、高齢者はもとより認知症の方や障害者への支援、子供の発達支援、メンタルヘルスケアなど多くの分野で必要とされており、クオリティー・オブ・ライフ(QOL)の向上についても期待されている。
リハビリテーションには、理学療法や作業療法、言語聴覚療法があり、それぞれ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(以下「リハビリテーション専門職」という。)が行っているが、その給与額は長年変化がなく、他職種と比較して伸び率が劣っている。処遇の低下は優秀な人材の流出や担い手不足を招き、リハビリテーションの質の低下にもつながりかねない。
国においては、令和6年度診療報酬改定において、リハビリテーション専門職の賃上げ措置を決定したところであるが、令和6年9月に実施された「リハビリテーション専門職の処遇改善に関する実態調査」において、医療施設では約3割、介護・福祉施設では約4割の施設で給与引上げが行われていない実態が明らかとなった。
リハビリテーション専門職の処遇改善は喫緊の課題であることから、今後は給与水準の底上げや継続的な昇給に向けた抜本的な対策が必要である。
よって国においては、リハビリテーション専門職のさらなる処遇改善の実現に向け、地域におけるリハビリテーション専門職の確保や処遇改善に向けた取組の推進を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月17日
提出先
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 内閣総理大臣
- 総務大臣
- 財務大臣
- 厚生労働大臣
災害時における避難所生活の環境改善を求める意見書
本文
我が国は過去何度も大規模災害に見舞われ、そのたびに多くの被災者が長期間、避難所で厳しい生活を送ってきた。避難所は、災害により生活拠点を失った被災者のよりどころであるが、水や食料、トイレ等の設置が不十分なケースや、また冷暖房の使用が限定的なケース、狭い空間での生活を強いられることもあるなど、生活の質には課題が多い状況である。加えて、災害発生による精神的ショックやストレス、避難生活下での持病の悪化、感染症の蔓延、エコノミークラス症候群の発症などで死に至る災害関連死が多数発生している。
能登半島地震における災害関連死は321人(令和7年3月6日現在)で、家屋倒壊などによる直接死の228人を上回っており、災害関連死を防ぐための避難所の環境改善は喫緊の課題である。
内閣府は、昨年12月、被災者の権利保護と被災者支援の最低基準を定めた国際基準である「スフィア基準」等を踏まえ、トイレ数や1人当たりの生活空間面積の数値目標を反映する形で避難所に関する取組指針・ガイドライン(以下「指針」という。)を改定した。
指針に「スフィア基準」を踏まえた具体的な数値が盛り込まれたことにより、自治体にはさらなる避難所の開設や、物資の備蓄等が求められるが、自治体によっては人員や予算に制約があることから、避難所運営に地域格差が生じる懸念がある。
よって国においては、災害時における避難所の環境改善を図るため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。
記
- 指針に沿った避難所の開設や、トイレ、キッチン、ベッド等の避難所用物資等の備蓄及び整備を行う自治体に対して財政支援を行うこと。
- 過去の大規模災害におけるトイレ事情を十分に踏まえ、衛生面に配慮した簡易トイレやマンホールトイレ等の整備及び普及に対して継続的に支援すること。また避難所となる学校等のバリアフリー化やトイレの洋式化を進めるための整備に対して支援すること。
- 一般避難所への避難が困難な方のための福祉避難所の充実に向けた資機材や福祉人材の確保などを推進する自治体の取組を支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月17日
提出先
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 内閣総理大臣
- 総務大臣
- 財務大臣
- 文部科学大臣
- 厚生労働大臣
- 内閣府特命担当大臣(防災)
愛玩動物を虐待から守るための法整備を求める意見書
本文
国は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動愛法」という。)を令和元年に改正し、動物虐待に関する罰則を強化した。動物虐待事犯の全国の検挙件数は、平成25年が36件で、令和4年が166件と10年間で4倍以上に増加しており、令和5年は過去最高となる181件となった。本県においても、令和3年に劣悪な環境で動物を多頭飼育した元ブリーダーが動愛法違反の疑いで逮捕され、動物の健康と安全を緊急に確保する必要に迫られる事案が発生した。
現在の動愛法では、適切に飼育管理をしていない者に対し、事態を改善させるための勧告や命令、立入検査、罰則の規定はあるものの、飼い主の所有権の制限に関する規定は定められていない。このため、飼い主が虐待をしていても、行政としては飼い主の所有権を放棄させることができないため、結果として、動物の安全の確保に支障が生じるおそれがある。
よって国においては、愛玩動物を虐待から守るため、飼い主が動物に対して虐待を行っている事実があり、行政が動物を保護する必要があると認めた場合には、飼い主の所有権を制限し、動物の保護ができるよう必要な法整備を行うことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月17日
提出先
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 内閣総理大臣
- 総務大臣
- 環境大臣
聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書
本文
加齢とともに有病率が高くなる加齢性難聴の患者数は、高齢化の進展に伴いさらに増加することが見込まれている。また、加齢性難聴は脳の活動の低下に加え、コミュニケーション障害や社会活動の減少を来すなど認知症の危険因子の1つとされており、患者の社会的孤立につながる可能性も懸念されている。
難聴への対策としては補聴器の利用が有効であるが、最近では収集した音を増幅して外耳道に送る気導補聴器や、骨導聴力を活用する骨導補聴器のほか、耳の軟骨を振動させて音を伝える軟骨伝導補聴器が開発されるなど、利用者に合った補聴器の選択が可能となっている。
しかし、国内の補聴器の利用率は、難聴と感じている方の15.2%で、そのうち65歳以上の方が占める割合は、僅か17.6%にとどまっている状況である。
急速に高齢化が進む中、補聴器をはじめとする聴覚補助機器等の普及を推進し、介護予防や生活の質の向上、社会参画の促進等を図ることは急務であり、難聴に悩む高齢者に対して地方自治体や医療機関等が早期に発見・介入し、適切な機器等の活用を含めた支援を行うことが重要である。
よって国においては、聴覚補助機器等の積極的な活用を推進するため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。
記
- 難聴に悩む高齢者が、医師や専門家の助言の下で、自身に合った聴覚補助機器等を積極的に活用できる体制を整備すること。
- 難聴に悩む高齢者と円滑にコミュニケーションを取れる社会の構築を目指し、合理的配慮の一環として、行政機関の公的窓口等における聴覚補助機器等の配備を促進すること。
- 社会福祉協議会や福祉施設等と連携した補助制度等の情報提供や個別相談など、普及啓発活動を強力に推進し、聴覚補助機器等のさらなる充実及び普及に向けた環境整備を進めるため、必要な財政措置を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月17日
提出先
- 衆議院議長
- 参議院議長
- 内閣総理大臣
- 総務大臣
- 財務大臣
- 厚生労働大臣
このページに関するお問い合わせ
静岡県議会政策調査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2559
ファクス番号:054-221-3572
gikai_chousa@pref.shizuoka.lg.jp