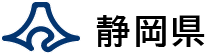「静岡県SDGsスクールアワード2024」審査結果発表!
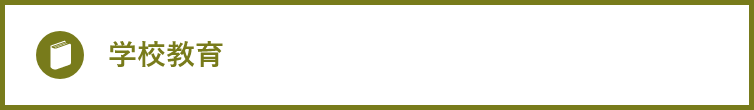
![]()

「静岡県SDGsスクールアワード2024」は、静岡県の子どもたちが持続可能な社会の創り手となり、県内にSDGsの理念を広く根付かせることができるよう、学校における児童・生徒のSDGs達成に向けた取組動画(90秒)を募集し、優れた取組を表彰するものです。本年度は96チームからの応募がありました。
令和7年2月17日(月曜日)には静岡市葵区の札の辻クロスホールにて表彰式を開催し、県教育長賞、優秀賞、審査委員特別賞、協賛企業賞を授与。また、昨年度受賞校の現在の取組についても紹介しました。
また、表彰式後には受賞校、協賛企業、審査委員が自由に交流し、歓談を楽しみました。
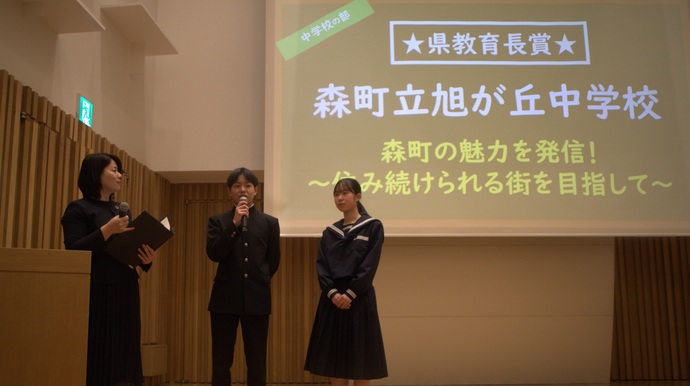


本アワードの審査に御協力いただきました審査委員の皆様、多大な御支援をいただきました「はごろも教育研究奨励会」様、企業賞を授与していただきました協賛企業の皆様のおかげをもちまして当アワードを開催することができましたこと、心より感謝申し上げます。
静岡県SDGsスクールアワード2024 審査委員会
| (審査委員長) | |
|---|---|
| 静岡県教育委員会教育長 | 池上 重弘 |
| (審査委員) | |
| 静岡県政策推進局長 |
山田 純哉 |
|
県校長会 |
渡辺 美輪子 |
|
県校長協会 |
遠山 一郎 |
| 静岡大学教育学部教授 | 田宮 縁 |
| はごろもフーズ株式会社取締役経営企画本部長 |
越野 勉 |
| NPOサプライズ代表 | 飯倉 清太 |
|
常葉大学 |
山本 千裕 |
「静岡県SDGsスクールアワード2024」へ御支援いただいた企業 様

静岡県SDGsスクールアワード2024協賛企業 様
| (敬称略) | |
|---|---|
| ELFIE GREEN 株式会社 | TOKAIグループ |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 静岡支店 | 株式会社天神屋 |
| 清水エスパルス | 第一生命保険株式会社 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 静岡支店 | 日本生命保険相互会社 |
| マックスバリュ東海株式会社 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 米久株式会社 | イオンリテール株式会社 東海カンパニー |
| 株式会社静岡銀行 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン |
| 株式会社ローソン | 静岡県JAグループ |
| 静岡ブルーレヴズ株式会社 | ジヤトコ株式会社 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 三井住友海上 |
| リコージャパン株式会社 静岡支社 |
受賞チームの取組
受賞校の取組動画を配信していますので、ぜひ御視聴ください。
小学校の部
(1) 県教育長賞
掛川市立原田小学校 異年齢高学年
「持続可能な原田地区を目指して」
【取組】 地域を盛り上げるために、「農産物」と「働く」をテーマに取り組んだ。「農産物」グループは、3つの作戦を実行した。リーフレット大作戦では、生産者の方に取材し、工夫してまとめた。レタシー大作戦では、廃棄されるリーフレタスの葉でドライレタスシートを作り、商品化した。オリジナル商品大作戦では、地域の農産物をトッピングしたピザを考え、販売することにした。「働く」グループは、地域や市内の様々な職種の方にインタビューをして、「働く」とは何かを考えた。地域を盛り上げ、たくさんの人を笑顔にするために、掛川市の間伐材を使った箸置きを販売する会社を立ち上げ、木の箸置きを作って販売し、木材と親しめるようにした。
(2) 優秀賞
熱海市立伊豆山小学校 5年生
「いっしょに ずっと 30年後の熱海の未来のためのSDGs」
【取組】 熱海市の観光客が集まる通りや浜辺のゴミ拾い活動に取り組んだ。ゴミの分別を通して、どのような人がどんな時にゴミを置いたままにしたりポイ捨てしたりしているのか分析を行った。また、拾ったゴミをただ捨てるのではなく、ゴミを減らすためにリサイクルする方法を考え、資源となるように処理した。さらに、浜辺のゴミ拾いの際に見つけた貝殻やシーグラスなど自然の中にある美しさを集め、造形活動に生かすことで海の良さを伝えた。
(3) 優秀賞
裾野市立富岡第二小学校 4年生
「SDGs活動し隊」
【取組】 SDGsとは何かを知るために、気になる目標について各自調べてスライドにまとめ、互いの発表を聞き合い学習を深めた。夏休みには、各自が考えた活動に取り組んだ。社会科に関連して、県の「水の出前教室」を受講し、水の大切さも学んだ。その後、自分たちで何かできることはないか考え、「SDGs活動し隊」を発足した。まずは、みんなで地域のごみ拾いを行った。拾ったごみは分別してきれいにし、重さを測って全校児童にポイ捨てしないよう啓発した。また、緑の羽募金活動も、自分たちでチラシ作成や広報活動を行い、休み時間や運動会に取り組んだ。給食時のプラスチックストローを節約しようと、ストローを使わない活動も続けている。
(4) 小学校の部 審査委員コメント(静岡県校長会 渡辺 美輪子 審査委員)
SDGsスクールアワードを受賞された小学校のみなさん、おめでとうございます。自分たちの住んでいる地域の現状を調べ、課題を知るだけにとどまることなく、その課題解決に向け、自分たちができることを「行動に移す」取組が高く評価されました。自分の住んでいる地域のよさや課題を見つけ、それを学校全体はもちろん地域にも発信し、自分たちの地域を自分たちで守ったり盛り上げたりする方法をいくつも考え実行した、その行動力に感服しました。活動が広がっていく中で、専門家や生産者・業者の方々と関わり一緒に課題解決に向かうなど、発展した取り組みも素晴らしかったです。その根底には、地域を愛する心=我が地域を守りたいという思いが原動力となり、様々なアイデアが生まれています。子どもは地域の宝です。これからも、地域のために自分たちにできることを見つけ、実行し続けていってください。
中学校の部
(1) 県教育長賞
森町立旭が丘中学校 総合学習Aチーム
「森町の魅力を発信!~住み続けられる街を目指して~」
【取組】 森町の特産品である柿とお茶を活用した品を作り、11月24日に開催される「もりもり二万人祭り」で販売することに決めました。まずは森町の次郎柿の歴史を知るために、市役所で資料をいただいて学習したり、柿のルーツについて地域の方からお話を聞いたりしました。その後、試作品を作る際には、賞味期限が近い柿を選んだり、夏の高温障害やカメムシの影響で売り物にならないものを提供していただいたりして、SDGsの目標に近づくようにしました。同時に、他のグループが森町のお菓子屋などを紹介したパンフレットや動画を作り、パンフレットをお客さんに配布したり、動画をyoutubeに載せたりして森町のことを知ってもらいました。
(2) 優秀賞
静岡市立長田西中学校 竹灯籠プロジェクト実行委員(1年学年委員)
「竹灯籠~中学生の夢が地域の未来を灯す~」
【取組】 10年後の理想の街づくりプランとして、中学生が提案した地域の課題の放任竹林を活用した竹灯籠プロジェクト(参道を竹灯籠で盛り上げ、夜景を見て長田の良さを実感しよう)を、昨年度から地域の方と協力して実現させています。今年度は、1年生全員と3年生で地域の方と一緒に竹灯籠を作り、徳願寺の参道に並べライトアップするだけでなく、昨年度使用した竹灯籠を竹チップにしてイベントに参加してくれた方々に配布しました。このイベントを盛り上げるために、地域の方と打ち合わせをしたり、放送やポスターを使って全校へ呼びかけをしたりしました。更に、小中学生が作成したポスターや俳句などを掲示し、参道を整備する活動を行いました。
(3) 優秀賞
森町立旭が丘中学校 総合学習C2チーム
「数年後、ホタルの住める小薮川を目指す!」
【取組】 私たちはホタルの住める環境について調べるため、水と環境を守る会の方にその条件や好む環境について聞きにいきました。榊原さんの話では、ホタルの餌となるカワニナが生息することで、ホタルが住めるようになることを知りました。しかし、カワニナは、コンクリートで舗装されたような環境では定着せず、大雨の時にはすぐに流されてしまうことがわかり、生物の生息数について実地調査を行いました。上流で、コンクリート舗装がされている境界を見つけ、その上下を観察すると生息数が大幅に違うことがわかりました。川付近の安全のため、小藪川も側面を固めており、その環境の変化によってホタルがいなくなってしまったことがわかりました。
(4) 中学校の部 審査委員コメント(常葉大学 山本 千裕 審査委員)
受賞された皆さん、おめでとうございます。審査を通じて、皆さんが主体的に活動し、様々な人を巻き込みながら確かな成果を挙げたことが評価されました。それぞれの住む町の魅力や課題を分析し知見を深めることは素晴らしいです。しかし、そこからさらに実際の行動へ繋げることは、大切であり必要なことであると同時に、多くの人が為し得ることではないかもしれません。挑戦の一歩を踏み出せる皆さんの存在は、地域の方々にとってはもちろん、私たちにとっても、希望のような存在です。ぜひ、今の授業や学校生活が終わった後も、今回の体験を忘れることなく、挑戦や失敗、学び、歩み続けること、楽しむこと等を続けていってください。そして、一緒に持続可能な社会や面白い社会を作り上げましょう!小さなことでも、私たち一人一人の思いと行動が世界を変えていきます。皆さんの情熱と行動に感謝しつつ、これからも期待しています。
高等学校の部
(1) 県教育長賞
県立浜松湖東高等学校 探究プロジェクト「子ども学習支援コトバショ」
「コトバショ」
【取組】 子ども学習支援の場「コトバショ」を高校生が立ち上げ運営している。4年前から月2回のペースで行っている。参加者を増やすために、近隣の小中学校に宣伝に赴き、ポスターを配布したり、昼の放送で呼びかけをさせていただいたりと活動を行ってきた。今年度は出張コトバショを行い、中学生に向けて夏休みに3日間学習支援を行った。
(2) 優秀賞
県立磐田農業高等学校 やらまいか班(生産流通科3年 西尾班)
「磐農生と巡る 食と農の魅力旅~ガストロノミーツーリズムへの挑戦~」
【取組】 磐田市の魅力的な食と農を伝えるバスツアーを昨年度から実施しています。そのために、食と農を掘り起こし、参加者が「また、買ってみたい」と思わせるように味わう・学ぶ・楽しむ体験を企画し、地元食材を使った商品「磐田オールピザ」を開発しました。具体的には、柿農家と無農薬栽培農家の収穫体験と試食、イタリア料理店でのランチ、お茶農家による“ほうじ茶体験”などを案内しました。アンケート結果は満足度93.3%、また購入したい90%でした。
(3) 優秀賞
県立御殿場高等学校 創造ビジネス科メディア観光コース
「地元産木材「ごてんばっ木」の認知度向上「この木なんの木ごてんばっ木」プロジェクト」
【取組】 昨年度、市の農林整備課と協働し、「ごてんばっ木」の認知度向上と木育の推進を目標に掲げ、イベントの実施を目指した課題解決策を提案した。今年度はその実施に向けて「この木なんの木ごてんばっ木プロジェクト」を立ち上げ、市や国立中央青少年交流の家、御殿場木材協同組合と協働し、産学官の連携のもとで活動を行った。具体的には、フィールドワークを通じて生徒が木の伐採や加工を体験し、そこで得た知識や経験を市民に還元するためのイベントを複数回実施した。これにより、市民が木の魅力に触れ、地元産木材に興味を持つ機会を創出した。活動を繰り返し実施内容をブラッシュアップしながら、2年間にわたり継続的に探究活動を行った。
(4) 高等学校の部 審査委員コメント(静岡県校長協会 遠山 一郎 審査委員)
高等学校の発表は、いずれも身近な生活での気付きから、課題を設定し、情報を収集、整理・分析し、関わりをもった人が幸せになるための方策を提案していただきました。
教育長賞の「子ども学習支援コトバショ」では、子供たちの学習が保障されるとともに、心のつながりが生まれました。生徒たちも子供たちを支援することで、学習することの大切や楽しさに気付いたと思います。このような循環が地域に広がっていくとよいと思います。優秀賞の「食と農の魅力旅」では、地域資源に着目し、地元の生産者と他地域の消費者をつないでいる点、「ごてんばっ木の認知度向上」では、地元産木材に着目し、伐採・加工・植樹のサイクルを見通して自然環境の保全を目指している点が評価されました。
発表校の取組は地域を活性化するとともに、静岡県の魅力・特色を高めています。また、自分たちの取組を発信することで、新たな気付きがあったと思います。その気付きを基に新たな課題を設定し、「すてきな未来」を目指して下さい。
特別支援学校の部
(1) 県教育長賞
県立静岡北特別支援学校 中学部 農園芸班
「地元の麻機みかんの皮でサシェを作ろう!」
【取組】 1学期に、制作したサシェをお世話になっている先生にプレゼントした際に、「いろんな香りや色があるともっといい」という意見をもらったことを思い出し、生徒の一人から「みかんの皮の香りをサシェに使いたい」という意見があった。そこで、みかん農家に皮の提供してもらい、それらをサシェに混ぜ合わせ、香りとデザインの改良につなげた。皮を乾燥させ、細かく砕き、加えることで、みかんの香りと砕いた皮のデザインのあるサシェを完成させることができた。
(2) 優秀賞
県立静岡視覚特別支援学校 中学部
「ぼくたちのSDGs~力を合わせて世界を変えよう~」
【取組】 コンタクトのアイシティが実施している「アイシティecoプロジェクト」に参加し、コンタクトレンズの空ケースの回収と、空ケースのアルミシールを剥がしてアイシティに届ける活動に取り組んでいます。空ケースをゴミとして燃やさないことでCO2削減につながります。また、回収した空ケースはリサイクルされ、その収益は目の病気の人のために寄付されます。家庭や職員、寄宿舎職員に加え、静岡南部特別支援学校や静岡県立大学短期大学部にも回収の協力を呼びかけました。校内外の依頼先に回収に伺い、集めた空ケースは一つずつアルミシールを剥がして分別します。校外学習では直接アイシティのお店に行き、集まった空ケースを届けてきました。
(3) 優秀賞
県立清水特別支援学校 高等部
「私たちが守る世界文化遺産」
【取組】 三保松原の美しい景観と、生活に悪影響を及ぼす海の潮風から守ってくれる松林をこれからも維持していくため、高等部と中学部の生徒で落ちた松の葉をかき集める松葉かきの活動に取り組んでいる。また、集めた松の葉と、牛乳パックの紙を使って、高等部と中学部の作業学習のグループが共同で「松葉紙」という再生紙を作っている。「松葉紙」を利用してメッセージカードやポストカード、土に還る鉢植えポットなどの製品開発に取り組んでいる。
(4) 特別支援学校の部 審査委員コメント(静岡大学教育学部教授 田宮 縁 審査委員)
受賞校のみなさま、おめでとうございます。エントリー校の取組は甲乙つけ難く、審査委員を悩ませました。
県教育長賞の静岡北特別支援学校・中学部農園芸班では、お世話になった農家のみかんの皮の大量廃棄という困り感を受け、「もったいない」という思いから活動が始まりました。大切な人の思いを自分ごとして捉え、サシェという形に生まれ変わらせ、双方の思いを多くの人々に届けたところが素晴らしいと思います。
また、静岡視覚特別支援学校の実践は、切実な思いを持って始めたコンタクトレンズの空ケース回収という行動が周りの人々を動かし、今後大きな潮流となることでしょう。環境問題だけでなく、健康や福祉などにも貢献できる実践です。清水特別支援学校の実践は、世界文化遺産を守る活動を通して、その恩恵を実感するとともに、廃棄物である松の葉を使った製品開発に至った活動のプロセスは持続可能な社会の構築に欠かせません。
審査委員特別賞
(1) 特別賞
島田市立島田第五小学校 SDGsフェアトレードプロジェクト 田中大翔
「フェアトレード商品を買って貧困をなくそう」
【取組】 1人で取り組むのでは課題解決が難しいと考え、ポスターをスーパーに掲示することを考えた。フェアトレードについて多くの人に知らせ、買ってもらうためにポスターを手作りし、2週間スーパーに掲示してもらった。スーパーのご厚意でフェアトレード商品の売り場を特設してもらうことができた。ポスターの掲示と特設コーナーにより、興味をもったり、購入したりということにつながった。
(2) 審査委員特別賞 審査委員コメント(NPOサプライズ代表 飯倉 清太 審査委員)
SDGsでも掲げられている貧困問題に取り組むため「3つの課題」を設定。そして、その3つの中から「自分ひとりが取り組んでも課題解決には難しい」と考えフェアトレード商品の購入と利用という課題に着目、学区内にあるスーパーに協力を依頼、承諾を得て「ポスター作成」「ポスター掲示」を実行しスーパー協力のもと2週間の販売を実施。
販売個数を増やすために商品棚を特別に設置してもらった結果、売上が前年対比170%まで伸びたとのこと。
イメージを浮かばせても実際に行動をすることはとても大変であるが、近隣の大人に相談をしフェアトレード商品の販売まで辿り着き、販売促進のための工夫をして売り上げを伸ばしたことは審査会の中でも大きな話題になりました。この素晴らしい行動力と分析力に審査委員特別賞をお贈りしたいと思います。おめでとうございます。
審査委員総評
総評(静岡大学教育学部教授 田宮 縁 審査委員)
静岡県SDGsスクールアワードも第3回を迎えました。受賞校のみなさま、おめでとうございます。受賞されなかった学校でも、一人一人が「持続可能な社会の創り手」として活動されておりました。
この3年間を振り返ると、SDGsの広報が中心だった中学校の部には大きな変化があったように思います。課題を自分ごととして捉え、地域の人たちと協力し、解決していこうとする活動が徐々に増え成果を上げています。また、4年前に浜松湖東高等学校の生徒さんが立ち上げたコトバショは、外国籍や貧困などの問題だけでなく対象を広げるとともに、学習支援だけでなくつながりの場としても役割も担うようになりました。活動の継続性、発展性は、素晴らしいものです。ユースの活動への期待は大きく膨らみます。
SDGsの達成には、一人一人が日々の生活の中でできることに取り組むことが欠かせません。例えば、ペットボトルの回収やリサイクルは大切なことです。しかし、それだけではプラスチック削減の解決には至りません。正解は一つではありません。ファシリテーターとして、おとなには俯瞰して課題を捉えることが求められています。企業や団体が提供しているパッケージのプログラムを安易に取り入れるのではなく、広い視野で検討することが必要です。
児童生徒の真摯な活動は、おとなにも勇気を与えてくれます。おとなも子どもと同じこと地平に立ち、すべての生き物のWell-beingの実現に向けてともに歩いていきましょう。
企業賞
(1) レタスはエルフィーで賞(ELFIE GREEN 株式会社)
森町立旭が丘中学校 総合学習B2チーム
「レタス・お茶・トウモロコシ!多くの人に森町産の食材を!」
【取組】 私たちは、森町の特産品を調べ、自分たちで広める活動をするために、商品に活用しながらPRすることにしました。商品を販売するには、技術が必要なため、夏休みには地元のスイーツ店に体験をお願いし、アドバイスをいただきました。試作を繰り返し、環境にやさしいこと、野菜をできるだけ使い切ること、森町以外の方にも魅力を伝えることを意識して準備を行いました。もりもりスープには、とうもろこしの甘々娘やレタスを使い、自然の味わいになるよう工夫しました。クッキーには、森町のお茶を混ぜてつくりました。店の名前、チラシつくりなど、一から手作りし、地域のイベントで森町以外の方にも魅力を伝えることができました。
【企業コメント】 森町立旭が丘中学校 総合学習B2チームの皆さん、おめでとうございます!
修学旅行で訪れた地域と地元を比較して問題点に気付いた点、素晴らしい気付きでしたね。お店への調査を元に経営の指針となる基本理念の大切さを学ばれた点も、一つの事象から膨らめて物事を捉えられており、学習の本質を体現されていたように感じました。
課題解決に向けて、地元の方へ思いを伝え・巻き込み・協力を仰いだことは、社会生活において活きた経験となるでしょう。大人になっても森町の良さを思い出して、ずっと住み続けてくれたらなと期待しています。
これからも地産地消を意識しレタスはELFIE GREENのものを食べて静岡県をより良い地域にみんなでしていきましょう!
(2) TOKAIグループ賞(TOKAIグループ)
浜松市立大瀬小学校 5年生
「大瀬未来プロジェクト」
【取組】 地域で自分たちにできることは何かを考えて、グループを作り取り組みました。それは、エコバックを作り、販売し収益を寄付できるか試すグループ、SDGsのことを伝えるために紙芝居を作るグループ、牛乳パックをリサイクルしていすを作るグループ、フェアトレードについて知ってもらうためにCMを作るグループ、輸送での二酸化炭素を減らすために地産地消のレシピを考え広めるグループ、ゲームでSDGsを知ってもらうグループ、へちまスポンジを広めてマイクロプラスチック減らそうとするグループです。
【企業コメント】 SDGsを地域にもっと広める為、「小学校5年生」の自分たちに何ができるのか一生懸命に考え、活動した過程がよくわかりました。
皆さんの考える課題、「エネルギーを使うには、必ず二酸化炭素が生まれ、地球温暖化になることが分かった。石油などを使ったものを使わない生活をすることは難しいことも分かった。」はその通りです。エネルギーの大切さと、環境に負担をかけない暮らしについての重要性を理解し、広く伝えようとする取り組みは素晴らしいと思いTOKAIグループ賞としました。
TOKAIグループはエネルギーを扱う企業グループとして、みなさんの地域の低・脱炭素に取り組んでいます。地域にSDGsをもっと広め、一緒にゴールを目指していきましょう。
(3) あいおいニッセイ同和損保CSV×DX賞(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 静岡支店)
焼津市立焼津中学校 保健専門委員会
「SDGsからの生活習慣~自分自身で健康管理できる焼中生になろう!~」
【取組】 アンケート項目を保健専門委員会で考え全校に実施し実態を把握した。その中で特に課題があると思われた項目について、保健専門委員で夏休みに調査を行った。(電子機器の使用・睡眠・理想の朝食について) 学校保健委員会では、SDGsからの生活習慣について、生徒一人一人に自分事として捉えてもらうために、健康づくり課の方々と綿密な打ち合わせをした。また、私たちの提案を劇仕立てにしたりクイズをしたり工夫をした。私たちが考える課題解決に繋がる会になったと思っている。また、SDGsからの生活習慣について全校に募集した川柳をカルタにし、作成者の思いを受け取った。まとめとして全校生徒一人一人が目標を立てた。
【企業コメント】 当社は昨年12月発足した、「焼津市スマートシティ推進協議会」の正会員として参画し、「市民の皆様のWell-beingの向上」に取組んでいます。
今回焼津中学校が取組まれた、「生活習慣を見直し健康でいること」は、SDGsの大事な精神であり、Well(良い)でbeing(状態)な取組と言えます。是非今後も自分の健康と地球の健康の為の取組を一緒に進めていきましょう!
(4) 株式会社天神屋賞(株式会社天神屋)
掛川市立原田小学校 異年齢高学年
「持続可能な原田地区を目指して」
【取組】 地域を盛り上げるために、「農産物」と「働く」をテーマに取り組んだ。「農産物」グループは、3つの作戦を実行した。リーフレット大作戦では、生産者の方に取材し、工夫してまとめた。レタシー大作戦では、廃棄されるリーフレタスの葉でドライレタスシートを作り、商品化した。オリジナル商品大作戦では、地域の農産物をトッピングしたピザを考え、販売することにした。「働く」グループは、地域や市内の様々な職種の方にインタビューをして、「働く」とは何かを考えた。地域を盛り上げ、たくさんの人を笑顔にするために、掛川市の間伐材を使った箸置きを販売する会社を立ち上げ、木の箸置きを作って販売し、木材と親しめるようにした。
【企業コメント】 少子高齢化、人口減少は原田地区だけでなく日本のたくさんの地域課題です。その解決のために、自分たちにできることが何かを考え行動されたみなさんに敬意を表します。よりよい地域にしていきたいという地域のみなさまの思いを実現できるよう、微力ながらお力添えできればと思います。受賞おめでとうございます。
(5) エスパルス賞(清水エスパルス)
県立御殿場高等学校 創造ビジネス科メディア観光コース
「地元産木材「ごてんばっ木」認知度向上「この木なんの木ごてんばっ木」プロジェクト」
【取組】 昨年度、市の農林整備課と協働し、「ごてんばっ木」の認知度向上と木育の推進を目標に掲げ、イベントの実施を目指した課題解決策を提案した。今年度はその実施に向けて「この木なんの木ごてんばっ木プロジェクト」を立ち上げ、市や国立中央青少年交流の家、御殿場木材協同組合と協働し、産学官の連携のもとで活動を行った。具体的には、フィールドワークを通じて生徒が木の伐採や加工を体験し、そこで得た知識や経験を市民に還元するためのイベントを複数回実施した。これにより、市民が木の魅力に触れ、地元産木材に興味を持つ機会を創出した。活動を繰り返し実施内容をブラッシュアップしながら、2年間にわたり継続的に探究活動を行った。
【企業コメント】 エスパルス賞の受賞、おめでとうございます。
「ごてんばっ木」という地域資源に目をつけ、その認知度向上にむけて、系統的・継続的な活動が行われている点を評価させていただきました。また関係各所を巻き込み、さまざまなイベントを通して地域活性にも一役買っている点は、弊社の事業の参考にもさせていただきたいと思います。エスパルスは、静岡市をホームタウンとしていますが、御殿場市とはファミリータウンパートナーシップ協定を結んでいます。SDGsの理念のもと、地域の持続的な発展のため、今後一緒の取り組む機会があれば嬉しく思います。
(6) 第一生命保険株式会社賞(第一生命保険株式会社)
城南静岡高等学校 普通科
「「とりこ弁当」「地産地消豚汁」で、規格外野菜を活用しよう」
【取組】 規格外野菜をつかったお弁当で規格外野菜の現状を周知することで、農家さんが規格外野菜を捨てなくてもよい仕組みを作りたいと考えた。静岡市特産の「葉ネギ」農家さんに、大量の規格外葉ネギが出て困っていると伺い、葉ネギを使ったお弁当を企画した。若い年代に規格外野菜を知ってもらうため、満足感があり、栄養も彩りも考えた「とりこ弁当」を、市内のお弁当屋さんのご協力を得て、学園祭や地域のお祭りで販売した。合わせて葉を使い、地産地消にこだわった豚汁も販売した。とても好評で、静岡特産ネギのおいしさと規格外野菜のことをアピールでき、私たちの取り組みを知ってもらうことができた。
【企業コメント】 日本の食料自給率は世界各国と比べると低い水準にあります。そこに問題意識を持ち葉ネギ農家さんの話を伺い、自分たちでできることを考え、実際に販売にまで至っている点がとても素晴らしいと思いました。学園祭だけにとどまらず、地域のお祭りや市役所での販売を実施されたことで、この活動を知った方々がフードロスについて考える良いきっかけになったと思います。
「つくる責任」から「つかう責任」に視野を広げ、日々の生活の中で活動を続けていただきたいです。
(7) 東京海上日動SDGs賞(東京海上日動火災保険株式会社静岡支店)
県立御殿場特別支援学校 中学部1組(肢体不自由クラス)
「中1組で知る・取り組むSDGs~コンポストで生む食材サイクル~」
【取組】 中1組では、2つのことに取り組みました。1つ目は、給食を残さないようにする呼びかけです。ポスターを制作し、食堂の前に掲示させてもらいました。また、ポスターを見てくれた人には「給食を残さないようにしよう」と言葉かけをしました。2つ目は、捨ててしまう食材を使ったコンポスト作りです。インターネットで検索して見つけたコンポスト。これならみんなでできそうと思い立ち、作り方や効果を調べました。実際に学校の食堂から出た捨ててしまう食材を使いコンポストを作り経過観察をしています。食材が分解され堆肥ができた後は野菜を育て、食材サイクルを目指します。
【企業コメント】 身近な給食の食品ロスに注目して、出来るところから行動を始めたことが素晴らしいお取り組みだと感じました。
食品ロスについて調べ、「もったいない」と感じた気持ちを行動に移したこと、そしてそれを学校全体に広めるためにポスターを作ったり、呼びかけを行ったりしたことは、大きな一歩です。また、捨ててしまう食材を使ってコンポストを作り、堆肥を使って新しい野菜を育てるというアイデアもとても素敵ですね。
みなさんの行動が、周りの人たちにも良い影響を与え、もっと多くの人がSDGsに関心を持つきっかけになることを期待し、東京海上日動SDGs賞とさせていただきます。
これからも皆さんで力を合わせて頑張ってください。
応援しています!
(8) 日本生命保険相互会社賞(日本生命保険相互会社)
静岡市立長田西中学校 竹灯籠プロジェクト実行委員(1年学年委員)
「竹灯籠~中学生の夢が地域の未来を灯す~」
【取組】 10年後の理想の街づくりプランとして、中学生が提案した地域の課題の放任竹林を活用した竹灯籠プロジェクト(参道を竹灯籠で盛り上げ、夜景を見て長田の良さを実感しよう)を、昨年度から地域の方と協力して実現させています。今年度は、1年生全員と3年生で地域の方と一緒に竹灯籠を作り、徳願寺の参道に並べライトアップするだけでなく、昨年度使用した竹灯籠を竹チップにしてイベントに参加してくれた方々に配布しました。このイベントを盛り上げるために、地域の方と打ち合わせをしたり、放送やポスターを使って全校へ呼びかけをしたりしました。更に、小中学生が作成したポスターや俳句などを掲示し、参道を整備する活動を行いました。
【企業コメント】 放任竹林の課題解決し、地域の魅力を向上するために、地域の方・全校生徒を巻き込まれたことに加え、小学生にもSDGsを体験してもらえるような様々な工夫が大変素晴らしいです。
また、参加者へのノベルティも昨年度に使用された竹灯籠を活用するというアイデアが持続的です。皆様でご覧になった長田の夜景は、大人になっても、きっと心の中に残り続ける良き思い出になったと思います。
弊社が目指す社会像である『誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会』という理念とも合致する本取組を企業賞といたしました。
(9) マックスバリュ東海賞(マックスバリュ東海株式会社)
県立浜松湖東高等学校 探究プロジェクト「子ども学習支援コトバショ」
「コトバショ」
【取組】 子ども学習支援の場「コトバショ」を高校生が立ち上げ運営している。4年前から月2回のペースで行っている。参加者を増やすために、近隣の小中学校に宣伝に赴き、ポスターを配布したり、昼の放送で呼びかけをさせていただいたりと活動を行ってきた。今年度は出張コトバショを行い、中学生に向けて夏休みに3日間学習支援を行った。
【企業コメント】 通信機器や技術の進化によって、様々な便利なツールやサービスが普及し便利になる一方で、人と人とのコミュニケーションが希薄になりつつある中、世代を超えた地域のつながりが生まれる、非常に素晴らしい取り組みと評価させていただきました。
コトバショを巣立った子が、次は教える側になって、未来に伝承されていくことを期待しています。
(10) 明治安田賞(明治安田生命保険相互会社)
県立田方農業高等学校 ライフデザイン科セラピーコース
「私たちのチカラで繋げる広げる認知症サポートの輪」
【取組】 「認知症カフェ」は認知症の予防や進行を遅らせることに有効であることから、函南町内に住む認知症の当事者の方やご家族、認知症予防の方を対象に学校の実習室を会場にして、日ごろ学習している「園芸福祉」を活用した農業高校生が企画・運営をする認知症カフェを年間7回、第1土曜日に開催しおり、今年で6年目になります。また3年前から認知症の方のケアをする「認知症マフ」の制作と普及活動についても地域のボランティアグループ、行政、病院と連携をしながら活動しています。まだまだ認知症マフを知らない方が多いため、今年度は講演会や福祉関係のイベントに行きマフの展示と説明をする普及活動を積極的におこないました。
【企業コメント】 今後の日本の課題として認知症が取り上げられています。日本全体の問題を取り上げており、よくまとめあげています。「認知症カフェ」や「認知症マフ」の活用、講演会やイベントを活用した普及活動を積極的に行っており、今後も上級生から下級生へ引継ぎ普及活動を継続的に行っていただきたいと思います。当社も「確かな安心をいつまでも」を経営理念として挙げています。全役職員が認知症サポーター育成講座を受講し、啓発活動を実施しています。是非当社と今後協調して認知症課題解決に向けた活動を実施していきましょう。
(11) 米久株式会社賞(米久株式会社)
裾野市立富岡第二小学校 4年生
「SDGs活動し隊」
【取組】 SDGsとは何かを知るために、気になる目標について各自調べてスライドにまとめ、互いの発表を聞き合い学習を深めた。夏休みには、各自が考えた活動に取り組んだ。社会科に関連して、県の「水の出前教室」を受講し、水の大切さも学んだ。その後、自分たちで何かできることはないか考え、「SDGs活動し隊」を発足した。まずは、みんなで地域のごみ拾いを行った。拾ったごみは分別してきれいにし、重さを測って全校児童にポイ捨てしないよう啓発した。また、緑の羽募金活動も、自分たちでチラシ作成や広報活動を行い、休み時間や運動会に取り組んだ。給食時のプラスチックストローを節約しようと、ストローを使わない活動も続けている。
【企業コメント】 SDGsについて、「知る」ことから一歩進んで、「行動する」ことの大切さに気がつき、身近なところからできることを考えて実践した素晴らしい取組みです。一人ひとりの行動が、地域や自然を守ることにつながります。その取組みを継続していくことも大切です。
私たち米久も、千本浜の海岸清掃や「しずおか未来の森サポーター」として富士山こどもの国の森林整備を継続して行っており、地域の環境や自然を守る活動に取組んでいます。皆さんの取り組みは、私たち米久の取り組みにも沿ったものであることから、企業賞を授与します。
(12) イオンリテール株式会社 東海カンパニー賞(イオンリテール株式会社 東海カンパニー)
三島市立坂小学校 心ほかほか 坂っ子隊
「地域と未来へつなぐ「坂っ子農園」」
【取組】 地域の遊休農地を活用し、児童が一年を通して様々な農作物の栽培や収穫を行った。作業の際には、地域学校協働本部をはじめ、地元の農家やJAの職員など、多くの方々に協力していただいた。収穫した野菜は、児童が持ち帰るだけでなく、給食の食材として使用したり、クラブ活動等で使用したりした。また、児童が保護者や地域の方々に販売する取組も行った。秋の収穫後には、児童会主催による「地域の方々に感謝する会」を開き、地域との交流を深めた。4年生以上の学年では、発展的な取組として「緑の少年団」活動も行い、紫陽花の植樹や砂漠化を防ぐための「沙漠教室」等を行ってSDGsに対する理解を深めた。
【企業コメント】 三島市立坂小学校のみなさん、受賞おめでとうございます。
三島市坂地区の遊休農地の問題を知り、遊休農地を活用した栽培・収穫を通して、毎日の食事がたくさんの人に支えられていることに気づくことができた素敵な取り組みでした。
動画では、野菜を元気よく収穫している楽しい様子や、地域のたくさんの人の笑顔を見ることができ、「坂っ子農園」を通した持続可能な農業の促進活動を楽しみにしています。
(13) 株式会社静岡銀行賞(株式会社静岡銀行)
掛川市立原田小学校 異年齢高学年
「持続可能な原田地区を目指して」
【取組】 地域を盛り上げるために、「農産物」と「働く」をテーマに取り組んだ。「農産物」グループは、3つの作戦を実行した。リーフレット大作戦では、生産者の方に取材し、工夫してまとめた。レタシー大作戦では、廃棄されるリーフレタスの葉でドライレタスシートを作り、商品化した。オリジナル商品大作戦では、地域の農産物をトッピングしたピザを考え、販売することにした。「働く」グループは、地域や市内の様々な職種の方にインタビューをして、「働く」とは何かを考えた。地域を盛り上げ、たくさんの人を笑顔にするために、掛川市の間伐材を使った箸置きを販売する会社を立ち上げ、木の箸置きを作って販売し、木材と親しめるようにした。
【企業コメント】 今まさに中山間地域での人口減少・少子高齢化という課題に直面している皆さんが地域を元気に、人々を笑顔にしたいという姿勢で様々な取組を考え、実行している点が素晴らしいです。
この取組の良いところは、「農産物」から地域の自然環境を守ることの大切さを学ぶだけでなく、同じ地域で暮らしている人を地域にとって大切な存在であると考え、その「働く」姿から学びを深めているところだと思います。
地域を守るためには、そこで活躍する「人」や「仕事」が欠かせません。これからも様々な人との出会いを通じて、自分にできることを考え、行動し続けてください。皆さんの活躍を楽しみにしています。
(14) セブン-イレブン・ジャパン賞(株式会社セブン‐イレブン・ジャパン)
城南静岡高等学校 普通科
「「とりこ弁当」「地産地消豚汁」で、規格外野菜を活用しよう」
【取組】 規格外野菜をつかったお弁当で規格外野菜の現状を周知することで、農家さんが規格外野菜を捨てなくてもよい仕組みを作りたいと考えた。静岡市特産の「葉ネギ」農家さんに、大量の規格外葉ネギが出て困っていると伺い、葉ネギを使ったお弁当を企画した。若い年代に規格外野菜を知ってもらうため、満足感があり、栄養も彩りも考えた「とりこ弁当」を、市内のお弁当屋さんのご協力を得て、学園祭や地域のお祭りで販売した。合わせて葉を使い、地産地消にこだわった豚汁も販売した。とても好評で、静岡特産ネギのおいしさと規格外野菜のことをアピールでき、私たちの取り組みを知ってもらうことができた。
【企業コメント】 セブン‐イレブン・ジャパン賞の受賞、おめでとうございます。
規格外野菜の廃棄という社会課題に着目され、商品開発というアプローチで問題提起・課題解決を目指す姿に感動感銘を受けました。また、若い世代をターゲットとして設定し、そこに向けた商品設計をしている点も素晴らしいと感じます。
弊社でも「明日の笑顔を共に創る」という目指す姿に向けて、農家の皆様と一緒に規格外野菜や果物の商品化に取り組んでおり、今回の皆さんの取り組みにとても近しいものを感じ、高い評価をさせていただきました。商品を作り、売るという行為を通じ、持続可能な社会を目指す皆さんの取り組みを今後も応援いたします。
(15) 株式会社ローソン賞(株式会社ローソン)
熱海市立伊豆山小学校 5年生
「いっしょに ずっと 30年後の熱海の未来のためのSDGs」
【取組】 熱海市の観光客が集まる通りや浜辺のゴミ拾い活動に取り組んだ。ゴミの分別を通して、どのような人がどんな時にゴミを置いたままにしたりポイ捨てしたりしているのか分析を行った。また、拾ったゴミをただ捨てるのではなく、ゴミを減らすためにリサイクルする方法を考え、資源となるように処理した。さらに、浜辺のゴミ拾いの際に見つけた貝殻やシーグラスなど自然の中にある美しさを集め、造形活動に生かすことで海の良さを伝えた。
【企業コメント】 みなさんが「30年後の熱海の未来を守りたい」との思いを掲げ、身近で日々おこる色々な問題を自分自身の事としてとらえ、みんなで調べて自分たちで問題点を考え、そのうえで目標を立て課題解決に取り組む姿が非常に素晴らしく感動しました。
今回取り組まれた課題のいずれもが弊社としても解決が必要です。その問題にみなさんのチャレンジしようとする姿勢が、わたくしたちの理念である“みんなと暮らすマチ”の人達の幸せにもつながっていくと考えています。
皆さんの取り組みで、熱海の未来がさらに良くなることを信じ、期待しています。
(16) 静岡県JAグループ賞(静岡県JAグループ)
森町立旭が丘中学校 総合学習B3チーム
「鍛冶島魅力発信基地から森町をPR!食と体操で魅力と元気をお届け!」
【取組】 私達は、課題解決に貢献するために、活動のテーマを「森町の特産品を発信して、地域を活性化させよう」に決めました。食をテーマに修学旅行で訪れたことで、森町産の食材を食べてもらうことに着目でき、訪れたお客様が楽しいと感じる空間づくりをすることで、また来たいと思ってもらえるようにすることが目的としました。そこで、地域おこし協力隊の方が立ち上げた「たまどん」という古民家を改装したお店で販売させてもらうよう協力を依頼し、8月に1回目、11月に2回目の販売を実現できました。宣伝広告を出したこともあり、多くのお客様が来店し、2回目には、海外や他地域からのお客様とも交流できました。
【企業コメント】 このたびは、企業賞の受賞おめでとうございます。
貴校は、修学旅行での学びを活かし、森町の特産品を使った商品開発・販売を地域一体となって行い、特産品の認知向上による地域活性化に取り組む姿勢が感じられました。
また、森町を訪れた方と森町版ラジオ体操を通じて交流し、地域の魅力を積極的に発信しており、多角的なアプローチで地域の活性化に貢献されていると感じ、企業賞に選考しました。
生徒の皆様のますますのご活躍を心から祈念申し上げます。
(17) 静岡ブルーレヴズ賞(静岡ブルーレヴズ株式会社)
県立浜松特別支援学校 高等部1年
「遠州灘の豊かさを守ろう!」
【取組】 私たち、浜松特別支援学校高等部1年生は、1年間を通じて、SDGsの学習をしています。特に「14 海の豊かさを守ろう」について力を入れています。5月と10月に「江之島クリーン作戦」として中田島砂丘のごみ拾いを行い、1月にも行う予定です。活動の輪を広げようと、近隣の浜松江之島高校生にも声を掛け、一緒に活動に取り組みました。10月には校外学習で浜名湖体験型学習施設ウォットへ行き、遠州灘や浜名湖を守る方法について学習しました。
【企業コメント】 昨年から継続した活動であること、今年度は近隣の高校とも連携することでより多くの人と清掃活動を行ったことが評価できます。
静岡県は多くの地域が海に面しており「SDGs:14海の豊かさを守ろう」は非常に重要なテーマだと感じます。
是非、皆様の活動が静岡県民に波及させるだけでなく全国の皆さんに知ってもらえればと思います。
静岡ブルーレヴズも静岡県をホストエリアとして活動するプロラグビークラブとして、今後一緒の取り組む機会があれば嬉しく思います。
(18) ジヤトコ賞(ジヤトコ株式会社)
県立静岡視覚特別支援学校 中学部
「ぼくたちのSDGs~力を合わせて世界を変えよう~」
【取組】 コンタクトのアイシティが実施している「アイシティecoプロジェクト」に参加し、コンタクトレンズの空ケースの回収と、空ケースのアルミシールを剥がしてアイシティに届ける活動に取り組んでいます。空ケースをゴミとして燃やさないことでCO2削減につながります。また、回収した空ケースはリサイクルされ、その収益は目の病気の人のために寄付されます。家庭や職員、寄宿舎職員に加え、静岡南部特別支援学校や静岡県立大学短期大学部にも回収の協力を呼びかけました。校内外の依頼先に回収に伺い、集めた空ケースは一つずつアルミシールを剥がして分別します。校外学習では直接アイシティのお店に行き、集まった空ケースを届けてきました。
【企業コメント】 優秀賞及び企業賞受賞おめでとうございます。弊社も「アイシティecoプロジェクト」に参加しており、弊社の活動との親和性を感じました。
ゴミを減らすことを通じて資源を大切にし、CO2削減に貢献する活動につなげていること、目標達成に向けてボックスに回収量がわかる工夫や、校外にも協力の声かけとみなさん自身が回収に訪問されている点など素晴らしい取り組みをされております。
「僕たちだけでは難しいことも、まわりのいろいろな人と協力しながらできることがあるとわかった」とのコメントに、みなさんの活動が未来も世界も変える希望が持てました。今後も継続した活動になることを期待しております。
(19) 損保ジャパン賞(損害保険ジャパン株式会社)
浜松開誠館中学校・高等学校 SDGs部
「循環型社会実現のために、私たちができること」
【取組】 課題に対して、私たちは循環型の社会を実現することが必要だと感じ、様々な活動を行った。その大きな例が、企業とのコラボレーションによって実現したアップサイクル植木鉢である。この活動はSDGs部主導ではあるものの、学校で回収したペットボトルキャップから植木鉢を作成しているため、生徒1人1人がアップサイクル事業に携わっているという実感と、環境問題への当事者意識が生まれたと感じている。また、これらの活動を次世代へと繋ぐべく、小中学校への出張授業も行っている。自分たちだけで完結していては次に繋がらず、次の世代まで継続して取り組んでこそ、循環型社会が実現すると考える。
【企業コメント】 多くの人々がなかなか行動に移せない中で、自らが様々な活動を実現していくことで社会を巻き込み、真の循環型社会の実現に向けて取り組まれた点が素晴らしいと感じました。また、小中学校での出張授業をおこなうことで、次世代にまで続く取り組みへと進化させたことに、「社会全体の意識を変える」ことへの意思の強さを感じ、感動しました。若い皆さんが社会課題を本気で考え、悩み、数々のハードルを越えて実行に向けて動いたことに大きな価値があると思います。今後も若い皆さんの柔軟な頭で様々な課題に向き合い、トライ&エラーを繰り返しながら実現をしていくことを願っています。
(20) 三井住友海上賞(三井住友海上)
県立熱海高等学校 2・3年生総合探究「リノベーション班」「食班」
「竹取夏物語」
【取組】 熱海市役所に通学路(さくらの名所散策路)の竹伐採の許可を得て、生徒が伐採し、本校で以下について取り組んだ。
(1)伐採した竹を使用し、流しそうめんを実施した。鉈や鋸、やすりを駆使し、半割の竹や三脚、箸、麵つゆの器まで竹で作った。一日体験入学の日に合わせて流しそうめん実施し、放置竹林の問題を中学生にも解説した。
(2)竹灯籠を制作した。30cmほどにカットした竹にドリルで穴をあけて、オリジナルのデザインを作り、中にサイリウムを入れて点灯した。本校文化祭の最後に校庭で行った打ち上げ花火の際に、夜の階段に竹灯籠を並べて足元の安全を確保した。
(3)竹筒の中に米を入れ、探究の時間に作成した石窯の中で炊き上げた。
【企業コメント】 放置竹林は県内各地で問題になっておりますが、それを“楽しく”解決している点が素晴らしいと考え、選出させていただきました。昨今、自然災害が多発している中で、防災・減災取組の推進は欠かせません。本取組は、竹を伐採するだけではなく、竹を地域住民の皆様のWell-Beingに繋がる活用方法を見出し、広めていただくことに大きな価値があると考えます。また、熱海高等学校の皆様の強い熱海愛が今回の素晴らしい取り組みにつながったと思います。今後も美しい熱海を守る活動を続けてください。
三井住友海上でも防災取組や保険を下支えに、地域住民のWell-Beingにつながる取組に力を入れております。
(21) リコージャパン 静岡支社長賞(リコージャパン株式会社 静岡支社)
県立清水特別支援学校 高等部
「私たちが守る世界文化遺産」
【取組】 三保松原の美しい景観と、生活に悪影響を及ぼす海の潮風から守ってくれる松林をこれからも維持していくため、高等部と中学部の生徒で落ちた松の葉をかき集める松葉かきの活動に取り組んでいる。また、集めた松の葉と、牛乳パックの紙を使って、高等部と中学部の作業学習のグループが共同で「松葉紙」という再生紙を作っている。「松葉紙」を利用してメッセージカードやポストカード、土に還る鉢植えポットなどの製品開発に取り組んでいる。
【企業コメント】 本活動のタイトルに『私たちが…』、という自分事としてSDGsに取り組む姿勢が強く感じられ大変素晴らしいと思います。その上で世界文化遺産の保全活動のみならず、松葉を利活用した松葉紙や土に帰る植木ポットの製品開発に中等部の皆さんともコラボレーションして活動されており、皆さんで取り組んでいる点も高く評価致します。これからもSDGsのゴールを目指し、自分事として何ができるかを考え、一緒に活動していきましょう。
奨励賞
- 富士宮市立大富士小学校・5年生
「SDGs調べ隊」 - 島田市立島田第五小学校・SDGsジェンダープロジェクト 北澤美羽
「ジェンダー平等を解決しよう!」 - 島田市立島田第五小学校・SDGs自然保護プロジェクト 松島新汰
「森の豊かさを守ろう!」 - 伊豆の国市立大仁北小学校・5年生
「自然と共存」 - 森町立旭が丘中学校・総合学習B1チーム
「ジェンダー平等教育で生きやすい社会の実現を目指す!」 - 島田市立川根中学校・まちおこし
「桜 まちおこし」 - 島田市立川根中学校・まちおこし
「家山駅」 - 焼津市立港中学校・特別支援学級
「花は地域をつなぐ架け橋」 - 県立島田商業高等学校・地域ブランディング「地方創生SHIMASHO」
「島田商業「地方創生(竹あかり)」の取り組み」 - 県立富士宮東高等学校・ドリームプロジェクト
「パレスチナを知ろう」 - 県立掛川東高等学校・お茶むすめ
「お茶を通して住み続けられるまちにしよう」 - 県立伊豆総合高等学校・生徒会
「伊豆総生のボランティア」 - 静岡市立桜が丘高等学校・2年商業科「商品開発と流通」
「食品ロスへの課題解決~私たちにできること~」 - 県立科学技術高等学校・都市基盤工学科「広報宣隊伝エンジャー!」
「七夕豪雨から50年「過去から学び未来に繋げる」」 - 県立浜松商業高等学校・生徒会
「浜商魂~愛する街を守る~」 - 県立天竜高等学校春野校舎・1年生
「春野町の林業を知る」 - 県立富士特別支援学校富士東分校・マリンスイープ班
「1つのルアーがつなぐ未来~海中ゴミの分別とルアーの再生~」 - 県立静岡北特別支援学校・中学部2年生
「あさはた自然博士になろう!」 - 県立沼津特別支援学校・高等部 染色縫製班
「不用品を使った作業製品作り」 - 県立藤枝特別支援学校・高等部2年2・3組グループ(1)
「SDGsと私たちの食生活」
![]()
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3168
ファクス番号:054-221-3561
kyoui_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp